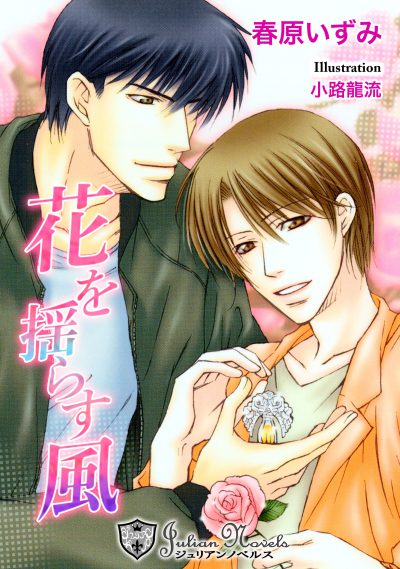秘密倶楽部の調教【書下ろし】
著者:村咲泉
イラスト:小路龍流
発売年月日:2015年12月11日
定価:990円(税込)
さあ、もっと大きく足を開いて 高校三年の八木沢理人は借金返済のため、男娼見習いとして会員制の秘密クラブで働いていた。繰り返される調教に耐えながら日々を送っているが、ある日、療養中の父を見舞った際、インド系ハーフのシンと出会う。彼は心優しい会社員で、インドの民間療法アーユルヴェーダを生かしたボランティアをしていた。シンの優しさに次第に引かれていく理人だったが、恋愛は禁止されている上、男娼としてオークションにかけられる日が近づいていた。