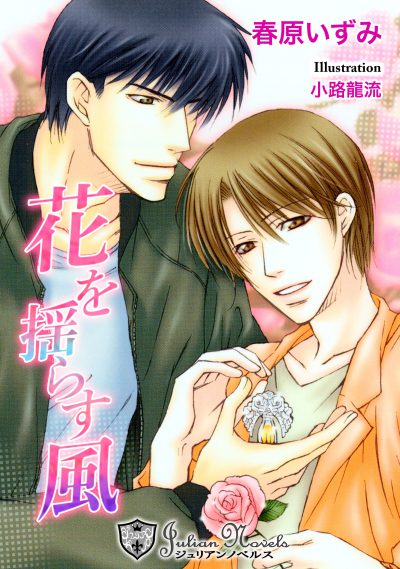「……っ、あ……」
顎が上がる。引き結んでいたはずのくちびるは甘くほどけ、喘(あえ)ぎ声を漏(も)らしてしまう。
――堕(お)ち、る……。
腰が、ひくつく。男の与える律動に、合わせるように。
体の内側に、他人の存在を感じさせられるのは初めてだ。知りたくなかった。知ってはならなかったはずのそれに、今、翻弄(ほんろう)されている。
「ひゃっ、く……っ」
濡れた音を立てているのは、自分自身の体だ。大きく広げられた足の間、本来ならば人目に触れさせるような場所ではない。そこが、はしたなくさらけだされている。
淫らな蜜にまみれ、肉欲そのものを受け入れていいような場所ではなかった。
けれども、今、そこが欲望の根源であることを思い知らされている。欲が、直接混じり合っている。
固く熱く、そして暴力的なほどの存在感があるものに、突き上げられる。揺さぶられる。一切の手加減なし、力任せの行為は、心まで粉々にしていくようだった。
せめて、痛みだけならよかった。そこを抉(えぐ)られ、揺すぶられることが、ただの苦痛であってほしかった。
それなのに、体は熱を帯びる。溢(あふ)れんばかりの快楽が、聖(きよ)見(み)を惑わす。
見開いた瞳に映るのは、冷ややかな男の顔だった。その顔に浮かぶのは、蔑(さげす)み? あざけり?
……いや、もっと暗く深く根源から湧き上がるような情動だろう。
激情に、聖見は穿(うが)たれている。肌と肌が触れ、欲望が直にぶつかりあう卑猥(ひわい)な音は激しくなり、聖見の体は快楽を味わわされる。
ふたりをつなぐのは欲望だけではない。怒りだ。それを自覚したとたん、うそ寒い想いに囚われる。
「あ……」
まなじりにも、濡れた感触。そこから静かにこぼれ落ちたのは、聖見の言葉にできない感情だった。貫かれ、揺すぶられ、ばらばらにされて。そして「なぜ?」と問うことも忘れるほどの快楽に犯された挙げ句の、悲鳴だった。
第一章
おととし。明治二十三年の浅草の大火で焼け落ちて、間にあわせのように再建された木造の教会の宿舎は、強い風が吹くと激しく梁(はり)が軋(きし)む。
その軋みに紛れて、扉を叩く音が聞こえてきた気がした。
佐宗(さそう)聖見はラテン語の綴り方の本から視線を上げる。
精巧な細工の時計は、丑(うし)の刻を過ぎたところを指していた。
――こんな時間に……。誰だろう?
不思議に思いながらも、聖見は立ちあがった。
そういえば、昨日の夜駆けこんできた男女も、今くらいの時間に扉を叩いたと、ふと思いだす。
「どちらさまでしょうか?」
木戸を開いて、聖見は顔を覗かせた。
「夜分に失礼」
真っ暗な夜の中。そこにいたのは、軍服姿の男だった。
秀麗な顔だちは、眼鏡が知性を引き立てている。全体のシルエットは細身かもしれない。けれども、修羅(しゅら)場(ば)馴れしている人間特有の威圧感が、彼からは醸しだされていた。
紺と緋色の制服。そして、軍刀を所持している……――憲兵だ。
彼らは軍隊の中の警察組織であり、将校にしか許されない騎馬や帯刀を許された、選良の集団だった。
男の肩越しにも、軍服姿の人間が数名いる。全員憲兵だろうか。
「私は、浅草の憲兵分隊の隊長、小磯(こいそ)大尉だ。あなたは、この教会の責任者か?」
小磯と名乗った男は、切れ長の瞳を細める。眼鏡ごしだったが、その眼差しは鋭い。
「いいえ。私は神父ではなく、まだ勉強中のものです」
聖見は、小さく首を振る。
教会で暮らすものらしく暗い色の洋装に身を包んでいるが、聖見は聖職者ではない。神学校への入学を目指し、神父の下で学んでいる身の上だった。
今、この教会の責任者で、聖見の師であるラ・ロシェル神父は、本国フランスに帰っている。日本に戻ってくるのは、来月の予定だ。
「神父さまは不在で、私が留守を預かっています。憲兵さんとは、珍しいお客さまですが、どのようなご用の向きでしょうか」
ごく静かな口調で、聖見は尋ねる。
そう言いながらも、頭の片隅を昨日逃げこんできた男女の姿がよぎった。憲兵が訪ねてくる理由なんて、彼らしか考えられない。
そうだとしても、絶対に秘密にしなくては。
聖見は顎を引き、真っすぐに小磯と名乗った大尉を見つめる。憲兵たちの不審を誘うような態度にはなっていないかと、そればかりが気になった。
「昨晩、逃亡兵がこの教会に逃げこんだという情報が入った」
小磯と名乗った憲兵は、威圧感のある低い声で言う。彼には、ある種の確信もあるようだった。
「中をあらためさせてもらう」
「お待ちください」
憲兵を口先でかわせるほど、聖見は世馴れていない。けれども、ここで言いなりになるわけにもいかなかった。
この教会を頼って、逃げてきた人たちを守るために。
「敷地内の施設では、子どもたちが眠っています。また明日の朝にでも、あらためていただけませんか?」
「子ども?」
小磯は、いぶかしげに目を細める。
「この教会には、孤独会という身よりのない子どもたちが住む施設が併設されています」
喉が渇く。
聖見は緊張しきっていた。