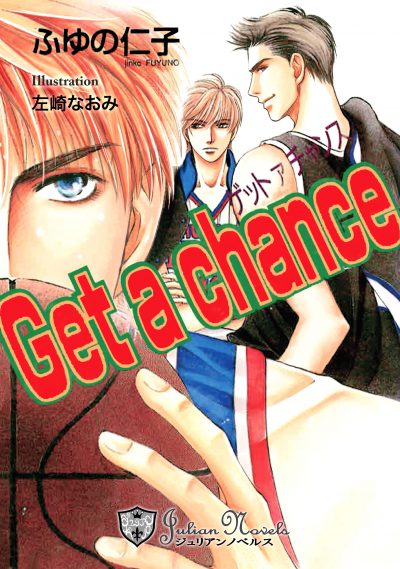官能のスパイラル【特別版イラスト入り】
著者:ふゆの仁子
イラスト:みささぎ楓李
発売年月日:2015年03月06日
定価:935円(税込)
背徳感が、より2人を高めていく 順調な仕事に、申し分のない妻――大手企業の営業で出世コースを歩みながら、加嶋雅之は欲求不満にも似た違和感があった。その渇きを潤すため、あるパーティーに参加し、艶めいた瞳で積極的に自分を誘う男、瀬上と一夜を過ごす。男を煽る仕種、巧みなキス、甘い喘ぎ――。強烈な記憶を残したまま消えた彼を忘れられない加嶋。そんな折、公の場で偶然瀬上と再会を果たした加嶋は、己の求めるまま瀬上との情事に溺れていくが……。狂うほどの衝撃と果ての内欲望、エゴイスティックな愛の結末は?