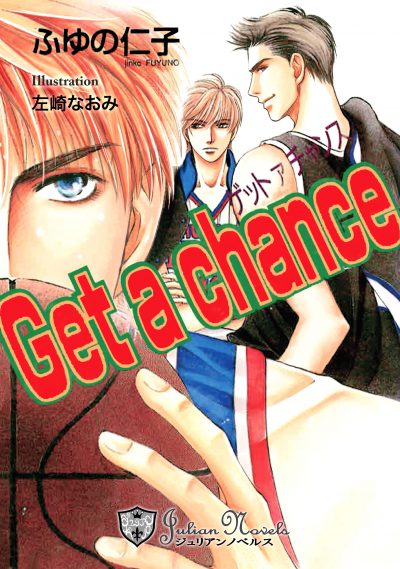プライベート・レッスン【特別版イラスト入り】
著者:ふゆの仁子
イラスト:秋月千璃
発売年月日:2015年04月03日
定価:935円(税込)
「秀朗」「……触って」 いまどきの若者らしい外見で遊び慣れている香野秀朗(18)と、純粋栽培で世間知らずの大学院生・諏訪部祐喜(28)は、年の離れた幼馴染み。2人はしっかり者の秀朗がのほほんとした祐喜の面倒を見るという関係だった。そんなある日、昔振られた男と偶然再会した祐喜が、なんと彼とつき合いはじめることに。そのうえ恋愛経験のない自分にその方法を教えてほしいと、秀朗にもちかけてきたのだ。断り切れずに恋愛教授を引き受けた秀朗だが、祐喜の幸せを望む気持ちとは裏腹に、理由のわからない苛立ちが募っていき……。