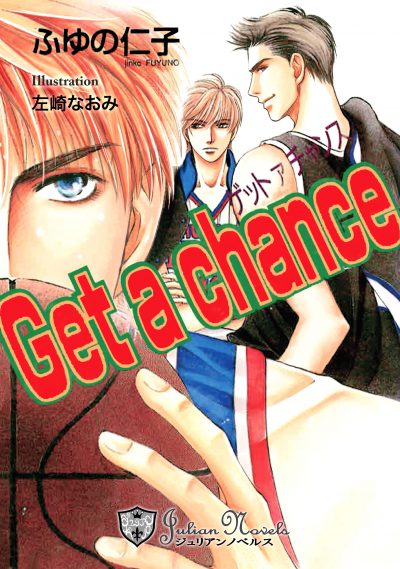ノスタルジック・ラヴ【特別版イラスト入り】
著者:ふゆの仁子
イラスト:金ひかる
発売年月日:2015年05月01日
定価:935円(税込)
こんなにして。絶対気持ちよくしてやるで……俺ん気持ち、わかって 一哉と茂人。子供の頃の約束がまた二人をふるさとで再会させたのだが…(なつまつり)。 幼馴染の広に想いを打ち明け同じ大学を目指す約束をした義秀。しかし思うように成績は伸びずそのあいまいな態度に二人はすれ違っていく…(秋の気配)。太と孝治は相思相愛の恋人同士だったのだが、お互いの将来を考えて出した結論は…(最後の初雪)。当たり前にあったものがいつかは消えていく切なさにも似た、3組の恋人たちの未熟さと切なさ。