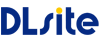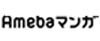大正濡恋譚~閨の生徒は年下子爵~
著者:麻倉とわ
イラスト:小路龍流
発売年月日:2022.12.30
定価:990円(税込)
大正十二年――伯爵家の令嬢・鞠子は家の借金のため天部子爵家の使用人となり、三歳年下の英国から戻ってきた天部家の次男・謙二郎の家庭教師となる。幼少期に交流のあった幼馴染である二人は、互いに成長した姿に惹かれあう。「どうか教えてください、先生。日本では、男女がどんなふうに愛し合うのかを」。鞠子は謙二郎に交際経験がないと打ち明けられ、跡継ぎとして問題ないように男女の営みを教えることになり――!?