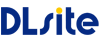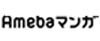白猫族のわたしに、黒犬族の幼馴染との結婚命令が出ました!
著者:百門一新
イラスト:龍 胡伯
発売年月日:2023年1月27日
定価:990円(税込)
あるとき、猫族のメイは異種婚が決まったことをいきなり告げられる。しかもその相手は、子供の頃からいがみ合ってきた犬族のイヴァンだった。〝神様〟である獣人の異種婚は、子をなすことが重要であるが、イヴァンが自分に欲情するはずがない。そんなメイの予想とは裏腹にイヴァンは子作りに積極的で、しかも甲斐甲斐しく世話まで焼いてくれる。それはあまりに彼の印象とかけ離れていたが、その尽くしっぷりにメイもしだいに胸をときめかせるようになって……。