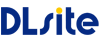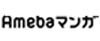どSなバーテンダーとバリキャリOL~上手にできたらもっとHなご褒美をあげるよ~
著者:叶 マリン
イラスト:みささぎ楓李
発売年月日:2022.12.30
定価:990円(税込)
IT企業で働く二十代後半のOL、唯が、仕事帰りに時々ふらりと立ち寄るバーのオーナーバーテンダーの川上さんと親しくなり、「二人で二軒目に行きませんか?」と誘われるところから始まるお話。そして会社では、わんこ系イケメンの一之瀬が、何かと唯に声を掛けてきて…。ある日、仕事上のミスを修正するため徹夜覚悟で唯が仕事をしていると、助け舟を出してくれたのが一之瀬で…。恋にも仕事にも手を抜かず、真摯に向き合うバリキャリOLの恋愛模様。