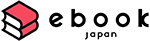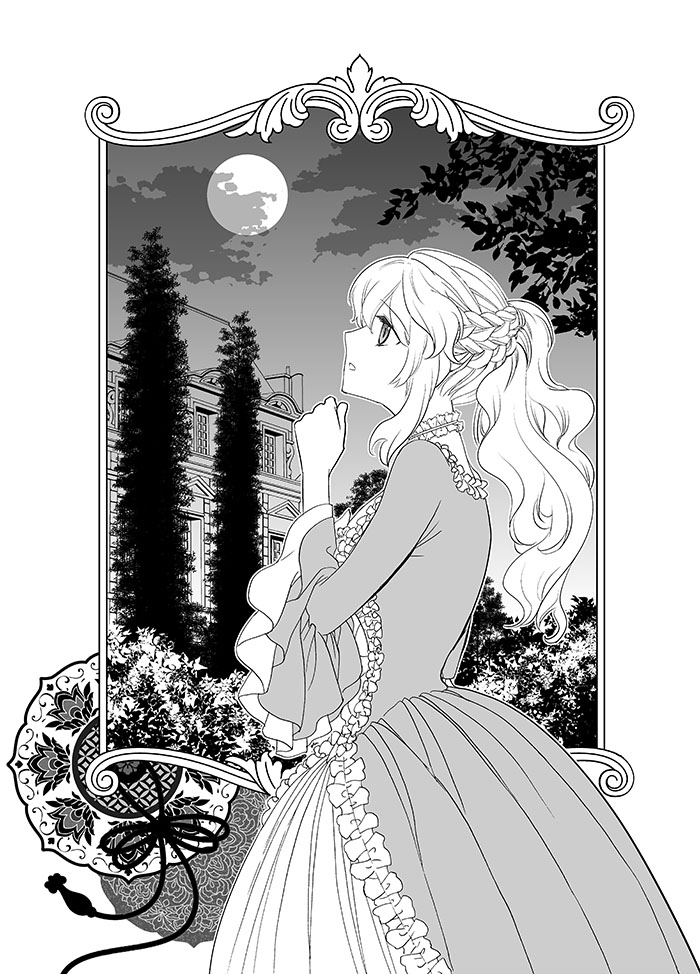第一章 クロシェディーユルーヴ学園へ
いつもミレイユは思っている。「わたしはこの世界の異端者じゃないの?」と。間違ってこの世界に生まれてしまったのではないかと。
立憲君主制の王国、ブルダリアス王国。ミレイユはこの国の司法官であるベルジュ伯爵家の娘として生まれた。兄に姉、妹に弟たちは皆『普通の貴族の子女』として問題なく振る舞っている。誰もきょうだいたちを「おかしな子」と言ったりはしない。そう言われるのはミレイユだけだ。自分のなにがおかしいのかミレイユにはわからない。ミレイユの生まれ育ったのは代々司法官を輩出する家で、直接関わることはなくてもミレイユの耳にもいろいろな判例が届く。その話をする中で家族も使用人も家庭教師も皆がミレイユを「変わっている」と言うのだ。
(でも、その人が生まれ持ったどうしようもないことが理由で処罰の内容が変わってくるとかおかしくない?)
同じ事件、たとえば人殺しをした者が裁かれる。同じような内容でも貴族と庶民では罪科が違う、ましてや流民ともなればブルダリアス王国の民に怪我をさせただけで(仮に事故でも)死罪になるというのが型どおりの判決だ。
「だってそんなの、あたりまえでしょ?」
ミレイユが疑問を口にするたびに両親やきょうだいたちは呆れ顔だ。
「身分が違うのだもの。なぜ同じように考えられるの? おかしなことを言う子ねぇ」
いや、だって……でも、と反論したくても材料がない。「どこでそんなことを教えられたの」と言われることもある。どこで教えられたのか、ミレイユにもわからない。ただ理不尽だと思うことがしばしばあるのだ。そんな、この世界での特殊な考え方がミレイユのどこから生まれてくるのかわからない、ただ「変わった子」というレッテルを甘んじて受けるしかないのだ。
ミレイユは不安だった。父が来年十六歳になるミレイユを国内最高ランクの教育機関である学園に入学させるというのだ。この国の誰もが知っている一流の学園だ。ベルジュ伯爵家の娘として両親の見栄もあるだろう、それ以上にその学園が何人もの優秀な人物を輩出しているのも確かなのだ。ミレイユの父(現司法執行官長)もこの学園の出身だ。
ミレイユが不安なのは、その学園が全寮制であることだ。実家を出て学園で生活するようになるのだ。そこでも「変わった子」として扱われるのだろうか、嫌われるのではないだろうか、友達もできないのではないだろうか。実家ではなんのかんのいっても家族なのだから受け容れてもらえている、一方で学園で交流するのは他人ばかりだ、変わった感覚を持っている(らしい)ミレイユはどのような扱いをされるのだろうか。それを思うと恐ろしい。
それでいて同時に、新しい環境にわくわくしている自分もいる。相反するふたつの感情に揺り動かされるミレイユは自室の窓の外を見た。
今は夜で、明るい月が見える。それでももっと明るい夜を知っているような気がする。月明かりだけではなくもっとたくさんの明かりが輝いていて、夜でも屋外で本が読めるような夜をミレイユは知っている。
(なんなんだろう……これ)
胸を押さえてミレイユは大きく息をつく。こういうところが、家族に「変わっている」と言われる一因だ。家族を困惑させるさまざまな言動のほか、ミレイユ自身にも理由のわからない懐かしさのような感覚は家族にも説明できない。
大きなため息とともにミレイユは部屋の奥の飾り机を見やった。優美な猫脚の机の上にあるのは手紙だ。金色の封蝋は破られている。中から覗く羊皮紙には飾り枠のような流れる文字で書かれた名称があった。
『クロシェディーユルーヴ学園』
「長ったらしい名前……」
家族の前では言えないことだ。ミレイユは小さく呟いた。その名前の長さは舌を噛みそうになるけれど同時に懐かしさを感じるのだ。なぜなのかわからないけれど。ミレイユはまた月を見た。今日は満月だ。月明かりが濃いとそれなりに庭園を見渡せる。ミレイユは夜の庭園に出た。
貴族の娘がひとりで外出など許されない。普通の貴族の娘ならひとりで外出しようなんて思いもしない。だがミレイユは違う、ひとりで行動するのに抵抗はない。自宅の庭なら危険はないけれどなにせ暗い、それでもひとりで夜の庭を歩くことに抵抗はない。今夜は月夜だからミレイユの足はますます軽やかだ。
ミレイユはなぜだか、月夜に惹かれる。なぜなのかはわからない、単に好きなだけだ。そういうところも「おかしな子」と言われてしまう原因なのだけれど。満月を見あげてため息をつく。
「やっぱりわたしは、おかしな子なのかな……? この世界の、異端者なのかな?」
そう口に出すと、とても悲しくなった。泣くようなことではないとは思っているけれど、それでもこの世界に居場所がない感覚は慣れるものではない。深くこぼしたため息の先、雲が晴れて月が姿を現した。金色の輝く月を見ているとなんとはなしに心が和むのはなぜだろうか。
「かぐや姫、的な……?」
自然に口から出た言葉にミレイユは「はっ?」と声を洩らした。口を押さえる。慌ててまわりを見まわす。
「なに……かぐや姫って?」
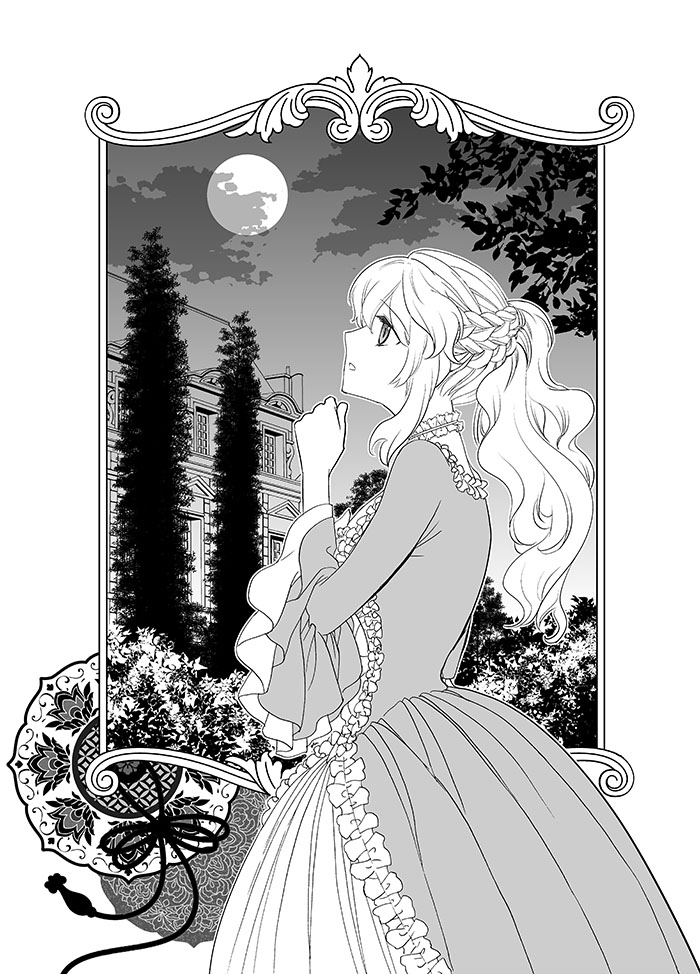
どこで聞いたのかもわからない謎の言葉にミレイユは首を捻った。自分の口から出たはずなのにそれがなんなのかわからない。また雲がするすると動き月は半分だけになった。ミレイユは、はぁとため息をつく。
(やっぱりわたしは、おかしな子なんだな……)
月夜の静けさは大好きだけれど、こんなふうに自分の異端を自覚するのは嬉しくない。ミレイユはふっと月から視線を逸らせて夜の庭をあとにした。
(こんな、わたし……学園なんかに入っちゃ迷惑になるんじゃ?)
そんな思いを抱きながらそっと寝室に戻ったのだ。
ミレイユの揺れる心を置き去りに、入学の日はやってきた。新しい生活のために新しい衣装をしつらえてもらった。クロームグリーンのドレスには淡いオーロラ色のレースが贅沢に縫いつけられている。舞踏会のドレスのようだ。変な子だと言われるミレイユだけれど貴族の娘に必要な教養はひととおり身につけていて特にダンスは好きだしうまいと言われている。ミレイユ自身もそれなりに自信があった。
自宅からの送りの馬車から降りて、華やいだ雰囲気の中「新入生はこちらに」と案内されるがままに煉瓦造りの建物の一階の部屋に入った。広い部屋だ、たくさんの椅子とテーブルが並んでいる。大きな窓には細かい目のレースのカーテンが揺れている。椅子には革が張ってあるけれど座り心地には期待できそうになかった。そもそもゆったり座るための椅子ではないのだ。これが集団学習のための教室か。今までは自宅で家庭教師に教わるばかりだった。同じくらいの年ごろの男女がたくさん集まっている状況に戸惑った。きょろきょろとあたりを見まわす。空いている椅子に腰を下ろした。
「こんにちは、初めまして」
隣に座っていた少女がこちらを向いた。にっこりと、それでいて探るようにミレイユを見る。慌ててミレイユは笑顔を作った。
「あ、初めまして。ミレイユよ」
「わたしはエレーヌ。ミレイユも新入生よね。きれいな髪! 金色がかった……シェルピンクってところかしら。目はプラムパープル? 濃いめの紫って表現すべきかな。素敵な色ね、珍しいわ」
立て続けのエレーヌの言葉にミレイユは目をぱちくりさせた。
「ありがとう……エレーヌの目は、素敵な青ね。濃い青で、とってもきれい」
「セレスティアルブルーって言って!」
「そ、そう? セレスティアル……あっええと、髪は栗色ね」
「わたし髪の色は、エトラスカンローズよ!」
胸を張ってそう言ったエレーヌに「そ、そうなんだ……ローズ……ああなるほど」とミレイユは頷いた。
「まっすぐで素敵。さらさらだね、よく手入れしているのね、エレーヌはきちんとしてるんだね」
「そう? わたしはあんまり自分の髪、好きじゃない。ミレイユの髪はくるくるふわふわで柔らかそう。触り心地よさそう。ねぇ、触ってもいい?」
「え、っ……」
ミレイユがなにか言う前に、エレーヌはミレイユの髪に触れてきた。ミレイユはびくりと大きく反応した。
「わっ、びっくりした。大袈裟ねぇ」
「ちょっと、ねぇ。触るのは……」
「いいじゃない、髪くらい。そんなに声をあげなくても」
機嫌を損ねたようにエレーヌは言った。唇を尖らせている。
(いいじゃない髪くらい、じゃないわよ)
ミレイユはそう思ったけれど口には出さない。確かに『髪くらい』だけれど馴れ馴れしいのは苦手だ。とはいえ今から全寮制の学園での集団生活が始まるのだ。寮ではふたり一室なことに加えて扉一枚隔てた向こうにもたくさんの学生がいる。皆と『仲よく』暮らしていかなくてはならないのだ。そう思うと憂鬱になった。エレーヌは不思議そうに首を傾げている。
「ミレイユ知ってる? 知ってるわよね、この学園の学生はみんな部活に入らなくちゃいけないの。ミレイユは何部にするか考えてるの?」
「部活……? そう、だね」
いきなり髪を触られて不愉快だとか突然なんの部活に入るかなんて訊かれて困るとか。エレーヌにはミレイユの心のうちがわからないようだ。ミレイユが返事をしたことに勢いを得たのかなおもぺちゃくちゃ話し続ける。ミレイユの知らないことばかりなのでありがたいといえばありがたい。とはいえミレイユが口を挟む余裕もないくらいに話し続けるのはどうかと思う。そんなふうに呆れるミレイユを前にエレーヌがふと声を潜めた。
「この学園、いろいろな身分の学生が入学するじゃない? 貴族も、庶民も」
なにが言いたいのだろう、ミレイユは眉をひそめた。エレーヌはそんなミレイユの反応に気がついていないらしい。
「でもそれって建前であるべきよね、身分の区別ってたいせつだと思うんだ。差別してるとかじゃないわよ、でもこの世界でたいせつなものってあると思うんだ」
「そ、うかも、ね……」
ミレイユの唇が少し震えたのもエレーヌは気がついていないのだろう。ミレイユはため息をつきそうになるのを懸命に堪えた。
(やっぱりこんなところに来て……わたし、やっていけるのかな。きっとエレーヌも付き合っていくうちにわたしをおかしいとか思うようになるんだろうし。なんか感覚が違うし……)
「ほら、噂をすれば」
「えっ?」
エレーヌが声を潜めた。教室中の空気がざわりとする。空気の動きはいい感じではない、ミレイユは眉をひそめた。
「ねぇミレイユ。あの子、知ってる?」
「知らない……かわいらしい子だね」
「かわいい? あの子が庶民の娘だって聞いてもそんなこと言える?」
「庶民?」
エレーヌの言葉になにもかも理解できたような気がする。入ってきた少女は小柄でかわいらしい。背中くらいまでの髪は灰色がかった茶色――グレージュ色ね、とエレーヌが呟いた。庶民だとかなんとか言っていたくせにやはりそういうところにはこだわるエレーヌに少し笑ってしまった。
少女の目は優しいミモザ色だ。あたりをきょろきょろと見ている様子は不安そうだ。エレーヌだけではない、教室中のすべての目が少女に向いている。
(あっ)
目が合った。縋るように見つめられる。視線を逸らしてしまった。するとエレーヌと目が合う。エレーヌは「困ったわね」とでも言わんばかりに肩をすくめた。
「もちろん学園が認めたんだから入学の資格はあるわよ。だけど、ねぇ……奨学金ですって……ねぇ? 庶民が、ねぇ?」
(なにが言いたいの?)
楽しそうに言うエレーヌにミレイユは眉をひそめるばかりだ。だからといってあの少女に同情しようとも思わないけれど。ミレイユは「変だ」と言われる自分がいかにこの学園で馴染めるかで精いっぱいなのだ、他人に関わっている余裕はない。あまりじろじろ見ては情が移るような気がして見ないようにした、けれど。
「あっ」
「えっ?」
気づけばミレイユは声をあげていた。少女のミモザ色の目を見ていると頭の中心からふわりと浮かんできたなにかがあるのだ。自分の中心にありながら今まで存在に気づいていなかった、なにか。少女は「?」と首を傾げている。その仕草もかわいらしいが、それ以上にミレイユの目を奪ったのはその少女の灰色がかった茶色(エレーヌ曰く、グレージュ色)の髪が彩る肩だ。そこには白いもふもふが乗っている。
(犬? 猫……違う、あれは……たぬき?)
「えっ? ええっ?」
ミレイユはまた声をあげた。
(たぬきってなに、わたしはなにを……えっ、なにそれ。違う、これは……え、ええっ?)
この感覚は初めてではない、自宅の月夜の庭園で突然浮かんできた奇異な言葉を口にしたときの感覚に似ている。そう「かぐや姫」と。
「どうしたの?」
「ううん……なんでも、ない」
少女は首を傾げている。白いもふもふに少女の白い頬がふわりと埋まった。すごく柔らかそうだ。ミレイユもあのもふもふに触りたい、頬を埋めたい。
「わっ」
そんなことを思っているミレイユの目の前、少女が歩いてくる。なぜかとても安堵した表情をしている。ミレイユも彼女を「庶民」と侮る者かもしれないのに? ミレイユは困惑した。
「こんにちは、初めまして」
「初めまして……わたし、こういう場所は初めてなんだけど」
「わたしもそうだよ、みんなそうでしょ?」
彼女は笑う、笑うととてもかわいらしい。不安そうな表情では感じなかった愛らしい華やかさで少女は言った。
「わたしはリディっていうの」
「そうなんだ。わたしはミレイユ」
リディの自己紹介にミレイユは答えた。それよりもなによりもリディの肩に乗っている白いもふもふが気になって仕方がない。もふもふの目はミレイユを見ている。視線が合って唖然としてしまった。
「どうしたの? あ、ぽん……? え、ええっ?」
リディが目を丸くしている。ミレイユの目はリディのそれよりも大きく開いた。
「ぽ、ん……?」
「ミレイユ、ぽんが見えるの?」
「ぽんっていう名前なんだ、それ?」
ミレイユが指をさす。リディは「うん」と頷く。ぽんの頭をよしよしと撫でる。ぽんの白いもふもふの中に見えていた黒いものがなくなった。「あれ、目だったんだ」とミレイユは驚いた。
(って、ぽん? ほんとうに、ぽんなの?)
ミレイユの頭の中がぐるぐるまわる。リディは、ぽんは、不思議そうにミレイユを見ている。ぽんのまんまるな黒い目を前に、ミレイユは「え、え、ええっ?」と間抜けな発声を繰り返してしまった。
「ミレイユ、ぽんのこと……知ってるの?」
「リディ、どうしてぽんと……一緒にいるの?」
ふたりの声が重なった。ふたりの目が合った。ぽんに視線を向けるとぷいと逸らされる。ミレイユは何度もまばたきをした。
「え、っ……あ、ああっ?」
ミレイユはまた声をあげた。リディの頭の上に数字が浮かんでいるのだ。指さした。リディはますます不思議そうに首を傾げた。ミレイユに見えるのは不可解で難解な文字だ。
「学力、体力……? 気力……」
(どうしてわたし、読めるの? あの、変な字……いいえ、変、じゃない……)
ミレイユの胸でどくりと熱いものが跳ねる。反射的に胸を押さえた。
(これ……『ラ・ブカツ!!』のパラメーター値じゃ……!?)
脳裏を貫いた言葉にミレイユは飛びあがった。リディもぽんも驚いている。「ど、どうしたの?」とリディが困惑しているけれどミレイユはそれどころではない。
(読める、あの、文字……読める、っていうか日本語!? 日本語じゃないの……なんでわたし、日本語だとか『ラ・ブカツ!!』だとか……なにこれ、えええっ、どういうことなの!?)
ミレイユは混乱の極みだ。そんなミレイユをリディが首を傾げて見ている。リディは不思議そうな顔をしているばかりだ。ぽんはなにごとかを言いたげにミレイユを見ている。ぽんに見つめられているとミレイユの頭の中にどんどん『ラ・ブカツ!!』の記憶が蘇ってくる。
(ぽん、そうだ! ぽんは『ラ・ブカツ!!』のチュートリアルキャラだから、プレイヤーのナビゲートをしてる……プレイヤー? わたし、ではない?)
ぽんは『ラ・ブカツ!!』のプレイを始めたときに遊び方を教えてくれる白いたぬきのようなもふもふの動物だ。ぱちぱちまばたきをしている。
「ねぇ、ぽん……」
「皆さま、着席なさい」
突然響いた女性の声に驚いた。手を打ちながら教室に入ってきたのは黒い衣装の落ち着いた雰囲気の女性だ、ミレイユの母くらいの年齢だろうか。教師なのだろう、教室は静かになった。彼女はこの学園での心構え、授業のスケジュール、毎日の過ごし方、などなどをてきぱきと指導していく。ミレイユはうんうんと頷いた。この教師は話がうまい。ただの注意事項なのにミレイユは聞き入ってしまった。
「皆さまには部活に入っていただきます」
(やっぱり……!)
ミレイユは「やっぱり」と思った。部活だ、ゲーム『ラ・ブカツ!!』ではプレイヤーは鈴神川学園に入学して部活に入るのだ。その部活で出会うキャラを攻略する。いろいろなタイプの個性的なキャラばかりだ。
(鈴神川学園……ん? クロシェディーユルーヴ学園……鈴(クロシェット)、神(ディユ)、川(フルーヴ)……?)
はっとミレイユは息を呑んだ。学園の名前をなんだか聞いたことがあると思ったのだ、意味が完全に当てはまるわけではない、それでもとても語感が似ている。聞いたことがあるような気がしたミレイユの感覚は間違っていなかったのだ。
(学園の名前、部活動、リディの頭の上に浮かんでた文字……なによりも、ぽん)
ミレイユはリディを見た。肩には白いもふもふが乗っている。もふもふはちらりとミレイユを見た、目が合うと慌てたようにあらぬ方向を向いた。
(ぽんが知っている? なにが起こっているのか教えてくれる?)
教師の声が滔々と響く。話題はいつの間にかこの学校の歴史へと移っていた。その間もミレイユはちらちらとリディを見た。おしゃべりをしている学生たちもいる中、リディはうんうんと頷きながら真面目に聞いている。エレーヌは彼女が奨学金を受けていると言っていたが、この真面目な様子なら納得だ。
ミレイユはちらりとエレーヌを見る。機嫌が悪そうに見えるのは気のせいだろうか。『庶民の娘が優秀で奨学金を受けている』ということが気に入らないのだろうとミレイユは思った。あるいは金を恵んでもらってまで学校に来ているなどと思ってそれを卑しいと思っているのかもしれない。
(そういう人、多いからねぇ……)
ため息をついた。ミレイユの実家は代々司法官を輩出しておりこの世界の裁判についてはミレイユもいろいろと見聞きしている。罪そのものではなく処罰のされ方が問題だと思う、そんな「おかしな子」と言われる理由に今のミレイユは気がつきつつあった。
(わたしは、この世界の人間じゃないんだね)
庶民の娘であるリディが遠巻きにされるのはこの世界で不思議なことではない。それでもミレイユはどうしても差別の感覚に違和感を持つしどうしても馴染めない。その理由が先ほどはっきりしたのだ。ブルダリアス王国、ベルジュ伯爵家の娘・ミレイユはこの世界の人間ではなかった――ゲーム『ラ・ブカツ!!』が存在した二十一世紀の日本に生きていた人間だったのだ。
とてもとても、驚くべきことだ。それでいてミレイユは驚くというよりも納得していた、安堵していた。気づけば胸に手を置いてしみじみと思い返していた。
(どういう理由でこの世界で生きてるのかな、わたし……)
ミレイユはちらりとリディを見た。やはり懸命に教師の話を聞いている、ミレイユの視線はその肩に向いていた。白いもふもふ、ぽんを見ている。ぽんはときどきミレイユを見る、目が合うとなにか言いたげに黒い目をぱちぱちするばかりだ。なにか言いたいのだろうか。話せないのかもしれない、『ラ・ブカツ!!』のぽんに声優はついていない、文字の台詞だけだった。
(ぽんがなにかを知ってるなら教えてほしいのに)
ちらちらと見ながらそう思ったけれど話せないのなら仕方がない、諦めてミレイユは肩を落とした。
(この後は製品版でお楽しみください)