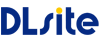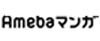ボーイッシュなおてんば令嬢は、訳あって姉の婚約者をオトしたい!
著者:ひなた翆
イラスト:蘭 蒼史
発売年月日:2023年5月26日
定価:990円(税込)
姉には婚約者がいるのに、ローランド地方の第三王子レオ・ダンケルドが結婚のためにハイランド地方にやってきた。大好きな姉には幸せになってほしくて、王女リンジーは、自分が王子の婚約者になると堂々と身代わり宣言をするが……父と姉から猛反対をうける。それなら姉の結婚式までに、王子を振り向かせればいいと考えた彼女は、あの手この手を使って王子を誘惑しはじめる。だが彼の周りには、何やら不穏な影がうごめいていて……?