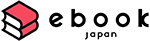雷撃令嬢と守りの魔術師〜研修は秘蜜の任務とともに〜
著者:ただふみ
イラスト:ひなた水色
発売年月日:2024.2.28
定価:990円(税込)
魔術師団に入団したレオニーだったが、入団式からトラブルにあい、幼なじみで婚約者のザイフリートに似た雰囲気の「男」に行為を求めてしまう。その後始まった研修生活では、寮の編入を余儀なくされ、新たにルームメイトとなったのは、そのザイフリート。さして自分に興味を持っていないと思っていたザイフリートに時折触れられ、困惑するレオニー。だが彼女の頭の中には、その「男」の存在がチラついてしまう。それでもレオニーは、ザイフリートがいいと願って……。