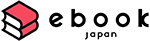銀狼帝の愛囚~復讐の姫は淫蜜にまみれて~
著者:麻倉とわ
イラスト:南香かをり
発売年月日:2022/3/25
定価:990
「皇后として大国レマンツェに嫁いできたセラフィーナ。しかしその心は激しく揺れていた。夫である皇帝シルベストルは狼の血を引く獣人で、もともと心惹かれていた相手だった。ところが大好きな従姉が狼になった彼に殺されたと知り、その復讐を果たすため妻になったのだ。初夜の床で刃を振るうも、取り押さえられ、離宮に監禁されてしまうセラフィーナ。新妻に裏切られ、怒りに震えるシルベストルに夜昼なく蹂躙されてしまうが――。」