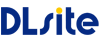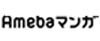続・ドSなバーテンダーとバリキャリOL~正直になれたら、またHなご褒美をあげるよ~
著者:叶マリン
イラスト:みささぎ楓季
発売年月日:2023年7月28日
定価:990円(税込)
恋人のバーテンダー・朔也と甘く濃密な年末年始を過ごしたIT企業勤務の唯。始業日より朔也の一族経営のホテルの予約システム改修リーダーに抜擢される。その矢先、朔也のバーは定休日が増え、忙しさと共に会える日が減ってしまう。 何かと距離の近いシステムアドバイザー・イケメンのロイと仕事を進めるも、チームの女子から不興を買い、遅れが出てしまう進捗に無理を重ねていく。その中、久々に会えた朔也との蜜月を迎えた翌日、不意に唯は吐血して倒れ……!?