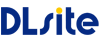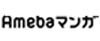執着するワンコな博士は、引き立て令嬢を召し上げる
著者:ただふみ
イラスト:緒田涼歌
発売年月日:2023.12.29
定価:990円(税込)
アリアーヌは薬学博士クローヴィスの助手として働く才女だ。美醜を重視する国民の感覚を逆手に取り、夜会では醜い化粧で《引き立て令嬢》となり妹たちのお見合いを成功に導いている。彼女の過労を案じたクローヴィスは夜会に行かずともいいようにと結婚を申し込む。予期せぬプロポーズに迷うアリアーヌだったが、クローヴィスの想いは仕事熱心だからではなかったらしくて――天然口説き魔かと思いきや……どこから本気だったの?