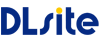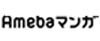三度目こそは、ハッピーエンドな結末を~精霊の加護を受けた姫の逆転人生
著者:ひなた翠
イラスト:南香かをり
発売年月日:2023年8月25日
定価:990円(税込)
オルトア王国の王太子、ノアの正妻候補に選ばれたエリン。しかし彼女は、その先に不幸な未来が待っているのを知っていた。彼女は、同じ人生をすでに二度繰り返していたのだ。三度目は違う結末を迎えるよう正妻候補から降りようとするエリンだったが、ノアがそれを認めない。それどころか、彼は正妻をエリンに決めているかのように振る舞う。これまでになかったノアの行動に戸惑うエリン。しかも彼は、この時点では知り得ないはずの情報まで知っていて……?