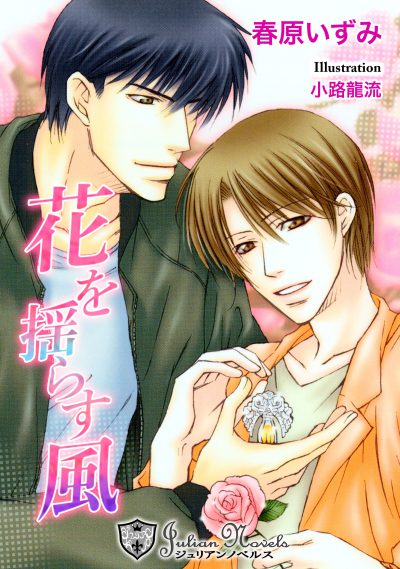恋のスクープは俺のもの!【特別版イラスト入り】
著者:宮川ゆうこ
イラスト:すがはら竜
発売年月日:2014年11月07日
定価:935円(税込)
おまえのいいところを全部俺に見せて 社会問題に鋭く切り込む硬派なスクープ記事で名を馳せる花形記者・小日向洋輔。彼に憧れて新聞記者の道を選んだ北山元気(もとき)は、偶然本社勤務の小日向と出逢うが、実際の彼は軽薄で手の早いタラシ男だった! いきなり「俺と付き合わない?」と口説かれたり、強引にキスをされたりで元気は大御迷惑。支局に赴任して、ホッとしたのもつかの間、現地で起こった殺人事件の取材にやってきた小日向を自宅に泊める羽目に。元気は、彼の手練手管で身も心もメロメロに説かされてしまい――!?